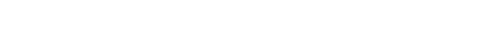ナラティブという考え方とグリーフ
社会構成主義
ナラティブや、ナラティブ・セラピーの考え方は、「社会構成主義(social constructionism)」という考え方に基づいています。この考え方は、「現実は社会的に構成される」「言葉は世界をつくる」などの主張が特徴であるといえます。人は自分を取り巻く世界や現実をありのままに捉えて、 理解するものであるとする考え方を否定して、人は自分の持つ認識の枠組みや知識を使って 世界を理解し、自分なりの意味を生成すると考えるのです。(この自分の見方による「世界と自分の姿」をC.M.パークスは「想定の世界」と呼んでいます。)そして、その認知はその人の存在する文化の枠組み、例えば、言語、歴史、象徴や隠喩などに影響されるといいます。また、個人も言語を使用して社会に働きかける(表現する)ことで、社会に影響を与えて行くと言います。
社会構成主義の発想は、人は自分を取り巻く世界や現実をありのままに捉えて、理解するものであるとする見方を否定する。人は自分の持つ認識の枠組みや知識を使って世界を理解し、自分なりの意味を生成するのである。しかも、経験を通して取得した知識や認識の枠組みは、社会が歴史的、文化的に相対的なものであることから、同じ事象や現象も、時代や地域によって意味が異なってくるとの考えに立つことになる。(中略)社会的慣行、社会構造と関連しながら、社会規範などを通して現実や事象は人に内在化すると主張する。この内在化によって、人は自らの主観的経験、自己イメージ、社会事象などを概念化し、現実を構成して行くとするのである。
(秋山薊二:「社会構成主義とナラティヴ・アプローチ-ソーシャルワークの視点から-」)
なかなか難しいですね。例えば、ここでは「おいしいケーキ」を取り上げる事にしようとおもいます(構成主義の考え方を説明するためなので、極端に単純化しています)。
- Aさんが、雑誌で有名な、とてもおいしいと言われる「Café Grief」のケーキを買ってきて食べてみた。ところが、結構いい値段がしたのに、大して美味しいと思えない。
- 「おいしいケーキ」と言うのは実体ではなく、多くの個人の評価の集合体という概念である。また、おいしいという概念は文化の枠組みによって違う。とても甘いケーキを美味しい、と言う文化もあれば、甘さ控えめを美味しいという文化もある。食べる人の年齢などによっても評価は違うだろう。だから、Aさんは「ケーキがおいしいかどうか」を評価しているのではなく、世間の「Café Grief のケーキはおいしい」という概念をAさんなりに評価しているのである。
- そこでAさんはブログに「Café Grief のケーキは高いばっかりで大したことはない」と書いてみたところ、賛同者が多く集まり、「賛成」だの「味が落ちた」といった意見が寄せられた。現在では「Café Grief」のケーキの評判は「とてもおいしいと」いう人と、「大したことない」に二分されているようだ。
- Bさんはそれをネットで読んだが、試しに、と思って買ってみた。その「とてもおいしい、と大したことない、に評価の二分されたケーキ」を食べた感想は「ま、こんなもんでしょ」という事だった。社会の評価が変化することで、同じケーキを食べるという経験が別の経験となったという事になる。
とこのように、構成主義の考え方では、人は言語を媒介にして、社会の常識、象徴などの影響を受けながら物事を意味として経験し、また、表現をすることで先の社会に影響を与えていくというのです。この相互的影響は上記の例のように単純なものではなく、非常に複雑な循環的仕組みと言えます。
グリーフに関していえば、ある人の喪失を全くの個人としてだけ認識することは不可能で、その喪失への意味付けには、遺された家族や、社会の常識といった概念の「すりあわせ」が必要だという事ができます。
ナラティブとは
物語としての人生
そういった構成主義の考えの中で、ナラティブという考え方が出てきました。ロバート・ニーメイヤーは、「人間には、生まれながらにしてどんな経験にも「ストー リー性」を求める習性があり、人間は、起乗転結のあるストーリーを構成しようとする」、と言います。この観点に関しては東京大学の早川正祐氏が、素晴らしい解説をしてくれているので紹介したいと思います。
なぜ自分の人生について述べられたことが「物語」として捉えられるのか。この点に関して重要なのは、人生についての描写が、「私はあのとき~の経験をした。それからこういう人に出会って~。そして、それがきっかけになって今~している」といった形で、時間軸に沿って表現されるということである。それは「私は今、机の前に座っている」といったある一時点における自分についての描写ではない。さらに、自分の人生についての時間軸に沿った記述は、単に出来事を年代順に羅列した歴史年表的な記述ではないという点にも注意しなければならない。むしろそこには、現在に至るまでの一定の「筋立て」があり、なぜ、自分が今ある状態に至ったのかが示されている(榎本博明:『〈私〉の心理学的探究:物語としての自己の視点から』1999)。もちろん、その記述内容がどのぐらいの時間幅を持っているのかに関しては、物語によって一様ではない。しかし、いずれにせよ、自分の人生についての記述がこのように一定の筋立てに従い時間軸に沿って述べられることから、それは自己「物語」として捉えられるのである。
早川正祐:「ナラティヴ・セラピーとケア ――当事者の物語の重視とは何か――」
また、早川氏によると、物語を製作するのに必要な構成要素(出来事)は「ストーリーに合うように」無意識的、恣意的に取捨選別される、という。「仕事のできる責任感の強い男」のストーリーを持つ人物は、そうでない都合の悪い人生のエピソードは自分のストーリーから排除する傾向がある。しかし同時に、この自分のストーリーは未来の認識や振る舞いに影響をあたえ、ストーリーの枠組みにあった人物像を描こうとする、つまり、行動がストーリーの後追いをすることがあるといいます。
お互い影響しあう物語
こういった人生のストーリーは言語を媒体として繰り返し表現されます。ニーメイヤーは私たちは「常に経験を語りながら人生のシナリオを作成している」と言います。
物語には語り手と聞き手がいることが必要ですが、この語り手と聞き手の相互作用が物語のコースを少しずつ変えていきます。私たちは、日常生活でも、語りつつ、聞き手の反応をうかがいながら、微妙に話し方、表現の仕方を変えることがあります。人は、自分の人生を共有してもらいたい、肯定してもらいたいという気持ちを持ち、こういった微調整は「自分のストーリーの有効性を受け入れてもらいたい」気持ちの表れです。
また、他者のストーリーや、会話の中で手に入れた語彙や、新しい隠喩、社会生活の中で受ける価値観も自分のストーリーに影響を与え、その物語の方向性はそれによって影響を受けて、自分で自分のストーリーは常に変化し続け、ある意味で未完の書籍に似ています。
私達は、自己の人生の著者であり、著書であり、 書評家でもある。
(Óscar F. Gonçalves:1995)
グリーフとナラティブ・セラピー
さて、このように、人生を「自ら書いた物語」とした考え方をした時に、グリーフはどうとらえられるべきでしょうか。
大切な人の喪失は、自分が描いてきた人生の物語の重要な登場人物を突然失ったのと同じです。今までのシナリオは全く役に立たず、ストーリーは大きな方向転換を強いられます。重要な登場人物を失ったストーリーは、あちらこちらで大きくほころび、どこから手を付けてよいのかわからないほどかもしれません。
ある男性との恋愛小説を書いていたのに、その男性から突然の別れを告げられた、としましょう。これまで考えてきた小説のプロットは台無しです。夢のような結婚式、かわいい子供、そんな目次はもう無効になってしまいました。この喪失は今の彼女(作者)にとっては「転落人生の序章」としか思えないかもしれませんが、それを何とか「新たな人生の出発点」に書き換えていく必要があるのです。
その時、「喪失を語る」のが有効だという専門家が多くいます。その一人、ロバート・ニーメヤーは、人は語る事で喪失の意味付けをすると言います。「私たちは、喪失体験を誰かに語る事で、自分を納得させ、他者にも理解を求め、その過程をとおして喪失と折 り合いをつけていく」、そして、喪失に意味を与えて行くと言います。さらに「自分を語る行為は、ミクロ・ナラテイブ(私的なディ テール)をマクロ・ナラティブ(社会的な一般化、社会的言説)にまで引き上げる認知、感情、行動的な作業」であると言い、グリーフに苦しむ人が、繰り返し、繰り返し語る死の状況も、大きな意味付けにつながって行くというのです。
語る事、の重要性がグリーフワークの中で重要視されている理由がここにあります。日記を書いたり、自分自身に語りかけたりするのに比べ、語り、聞いてもらう、と言う作業は双方向的で、ストーリーの空間は広がり、語彙と比喩は豊かで、メタファーが立ち上がりやすい環境と言えるでしょう。それぞれの社会と言語は、死に関して豊富な言説(死に関する表現)を持っており、そこから人は表現や常套句を取捨選択して使用していますが、他者と交わる中でその言説は広がりを見せ、最も適切な表現を見出す可能性が大きくなります。
一般的に多くの人は、信頼できる友人、家族や親族に喪失体験を語る事でこのストーリーの再編集を行っていきますが、中には専門的な援助が必要となる人もいます。そういったケースをナラティブ・セラピーと呼んでいます。先に「自己の人生の著者であり、著書であり、
書評家でもある」と言う考え方を紹介しましたが、その時セラピストの担う役割は編集者と言ってよいでしょう。著者の主体性は尊重しながら、読み、批評し、アドバイスをすることで、破綻したストーリーを別のストーリーにつなげる手伝いをすることが出来るのです。
更なる理解のために:言語と社会の認識、メタファー、繰り返し語る事
言語と社会の認識
ここで少し本筋とはなれますが、社会構成主義を理解するために、言語と社会の認識についてお話ししたいと思います。
言語学において、言語と社会の認識は非常に密接にかかわりあっていることが知られています。
ここでは、認知の切り取られ方について、ソシュールと言う言語学者による、言語と意味の二重構造を簡単に解説しておきます。 例えば英語のbrotherと言う単語を考えてみましょう、日本語では「兄弟」と訳されます。日本では子供の生まれた順番や年齢の上下が重要ですので、「兄」には歳が多い、と言う以上の意味(跡継ぎ、先輩)が付与されています。兄弟は兄+弟という二つのコンセプトが一緒になったもの、と言えるでしょう。一方、年齢の上下が重要でない英語圏のbrotherは「親を同じくする男の子供」というコンセプトであると言え、英語による「brother」は日本語の「兄弟」とは同じとは言えません。 様々な言語の「兄弟」という単語は、それぞれの言語特有の文化的価値が付与され(言語によって社会の認知の切り取られ方が違う)、完全に一致する事はありません。言語は単語と言う意味だけではなく、その言語や社会が規定する背景も伝え、言語と認知は切り離せない要因となっているとソシュールは述べています。このように言語は社会の認識と大きくかかわっているということが出来るのです。
メタファー
さらに、メタファー(隠喩)や例えが出来事のの認識を容易にし、生き生きとしたストーリーを描くのに重要である事も理解しすべきと思います。社会学者の勝又正直は、メタファーは「理解しにくいことを別の概念にあてはめる事で理解しやすくする」のだと言います。
人間が事態のとらえるその有り様は実はあまり多様ではない。自分の体で経験したわずかなパターンを使い回していることがしばしばである。そのとき人間は、慣れない事態を見立て(メタファー)によって慣れ親しんだパターンに還元していることがしばしばある。
そのためメタファーとも気づかないほど当たり前になっている多くの言い回しがある。
た とえば、「目玉焼き」というのももともとはメタファーである。さらに「男に捨てられた」というような言い回しがある。だが本来、「捨てる」ことができるの は品物である。つまりこの言い回しでは「私」は使い捨てされる「品物」に喩え(見立て)られている。さらに「捨てる」という言葉の連想から「さんざんいい ように使っておいて、ボロぞうきんのようにポイと捨てた」という具合にどんどん隠喩の中で連想が展開していってお話を作っていく(こういうメタファーの展 開のことをアレゴリーという) )。「別れた」を「捨てられた」と見立てることで、男女の別れ話は、品物を使い捨てる話へと移しかえられていく。つまり男女の別れの話(概念体系)が、も のを捨てる話(概念体系)へと写し取られていく。その写し取り(写像)の端緒となったのは、「別れる」という事態を「捨てられた」というたとえ(メタ ファー)で語ったことにある。そうすることで二人の別れの話は、ものを捨てる話へと写し取られて、ものを使い捨てる話(概念体系)のなかで理解されてい く。
レイコフという言語学者は、メタファー(隠喩)を「ある概念を別の概念と関係づけることによって、一方を他方で理解する」するという頭の働 かせかたである、と言っている。そしてAの概念体系の要素(たとえば「別れ」)をBの概念体系の要素(「捨てる」)に対応させ(写像し)、さらにその写像 をさらにどんどんして、Aの概念体系とBの概念体系が対応されることを「概念メタファー」と呼んでいる )。
人間が実感を込めて経験的に理解で きることの範囲というのは実は限定されたものである。私たちはそのままでは理解しがたい事態を、すでに慣れ親しんだお話へと移しかえ、それを展開していく ことで、そのままではなかなか理解できないような事態を、理解できるものへと変えていくのである。
私たちが慣れ親しんでいる常套句(クリシェ) はこうした陳腐な喩えによるすり替えに満ちている。しかしこうした陳腐な言い回しによるありふれた物語りの圧政の下で虐げれている自分が存在する。そのと き、それまでとは違う喩え(見立て)をすることで、自分を別の物語りへと解放していくことが求められるのかもしれない。
しばしば「夫婦の絆」と いう言い方がされたりする。「絆」とはもともとは「動物をつなぎとめる綱」のことであり、本来はメタファーである。だがもうメタファーであるを意識しない ほど当たり前になった言い方である。しかしその喩えで考えるかぎり、夫婦の関係は強固で、それを失った者は、まるで「糸の切れたたこ」みたいに思えてく る。でももしここで誰かが夫婦なんて「ポスト・イットみたいなもんよ」と言い出したらどうだろうか。この喩えは夫婦に対するまるで違った見方をもたらすか もしれない。
陳腐でそれだけに逃れがたい物語りのくびきから逃れるために、人はたとえ(メタファー)をつかい、それを種にして新たな物語りを生成していくのではないのだろうか。勝又正直のブログ「社会学しよう!」:ケアにおける語りのメタファーより
繰り返し語る事
先に、繰り返し語る事が物語の改編にとって重要である、という事を書きました。遺された者は往々に「死の様子」を繰り返し、繰り返し語ります。頭の中に死の様子をビデオのように流しながら、それを語り、「語る自分を聞きながら」さらに語っていきますが、物語を何度も語る作業は、ストーリー再編の草稿作成と言うべきもので、毎回、少しずつ違っていることがしばしばです。早川正祐氏によると「物語を製作するのに必要な構成要素(出来事)は「ストーリーに合うように」無意識的、恣意的に取捨選別される」と言うのですが、これはどう作用するのでしょうか。
例えば、病床の夫が最後に何かかすかにささやいた、とします。「・・・・・・う」。よく聞こえなかったが、あれは「ありがとう」だったのだろうか、と当初思っていた妻が、何度も語るうちに。「ありがとう」だったかもしれませんね、「ありがとう」だった、と変遷し、最終的に「夫は最後に「ありがとう」といって息を引き取りました」、と言うお話になる。そういう事だと私は考えます。最終的に再編されたストーリーは語る人のストーリーで、語り手がそのストーリーの中で生き生きと生きていくために、ストーリーは作られていくのです。
また、C.M.パークスによると、喪失直後より、1年程度たった時の方がより「亡夫の鮮明な記憶が残っている」と語る未亡人が多いといいます。繰り返し記憶のテープを再生することで、「何をどのように思い出すのか」のパターンが固着してくる証拠の一つと考えられないでしょうか。