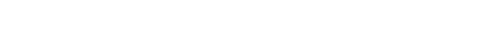葬儀、儀礼、墓の役割
葬儀の意味
葬儀は人が死を迎えたときに行う大切な儀式です。儀式、ですので、葬儀はしばしば没個性的に見えます。これには、大切な家族を失った遺族にとって、既に決まった形式、手順、作法があることで負担が減る、という面もありますが、現代の葬儀では、セレモニーとしての葬儀、習慣としての葬儀、社会的な対面としての葬儀といった、葬儀のある部分が独り歩きして、、その本来の意味をやや見失っているのではないでしょうか。
ここで今一度、葬儀の意味を確認してみたいと思います。
死者と対面し、死を確認する
当たり前に思えるかもしれませんが、葬儀の一連の儀式の中で、遺体と対面することが、物理的な死を確認する大きな助けとなります。遺体が見つからない、事故などで遺体の損傷が激しい、などの理由から遺体との対面が出来ない時は、「死が本当のように感じられない」こともあり、後に死の認識に問題がある(生還を信じていつまでも待ち続ける、など)事もあるほどです。日本の葬送に関する権威である碑文谷氏は、繰り返し行われる死の確認についてこのように述べています。
葬儀がこのような(闘病、臨終、通夜、葬儀、火葬という)プロセスと機能をもつのは、死というものの多面性、困難さに対応する知恵であったと思う。長い病気の末の死の場合には、事前に「予期さ れた死」があり、本人も家族もこれと向き合い、臨終の段階には「医学的な死」「法的な死」があり、通夜の段階では死の受容をめぐって相剋し、葬儀式の段階 で「宗教的な死」を体験し、告別式の段階で「社会的な死」があり、火葬の段階で「物理的な死」を体験する(中略)
葬儀とは、このように見てみると、死の事実性を次々と遺族に突きつけていくプロセスでもある。葬儀の段階を踏むごとに、死が夢ではなく現実であることの 認識を強いていく。したがって愛する者にとっては精神的には過酷なプロセスである。だが、これは必要なプロセスである。こうした曖昧さを取り去り、死の事実に向き合うことが大切なのである。碑文谷創:「葬儀のプロセスと機能」 (文中カッコ内は管理人加筆)
遺族に寄り添い、安心感を与える
葬儀には、一般的に友人親族が集い、その死が重要な出来事であることを改めて共同体として認識します。遺された者は、公に、安心して悲しむことのできる場を与えられ、また、その悲しみも、共同体に認識されることとなります。
葬儀に参列した者は、遺族に思いやりといたわりの気持ちを言葉で、あるいは態度で表現します。又、宗教的な儀式では、普段は信心深くない人も、共に故人の霊が安心できるところへ導かれるよう祈ります。
こういった環境の中で遺された者は、周囲の人間もこの死の重大性を認めていることを感じ、また、周囲のサポートが得られるであろうという安心感の中にグリーフの第一歩を踏み出します。
故人の人生を振り返り、故人に対する思いの表現し、故人を讃え、大切な関係を心に刻む
故人への思いを表現し、故人の人生を讃えるのに、葬儀は最適な場を提供します。遺された者は故人の生涯が価値あり、素晴らしいものであった事を讃えるため、それに見合った場を用意し、参列者を迎えます。最近は「故人らしい葬儀」が注目を集めており、以前の葬儀、告別式に比較して、その装飾やプログラム自体に故人らしさを表出させたいと考える遺族も多いようです。
また、遺された者は参列者に故人に代わって生前の交流と行為に礼を述べ、逆に
参列の人々は弔辞を述べ、故人がそれぞれの人に、それぞれの形で重要であった事を証言します。葬儀を通して、故人の事が鮮やかに思い出され、個人を中心に遺族、参列者が深い思いで故人に別れを告げるのです。
遺体を処理する
公衆衛生の観点から、火葬、または土葬によって遺体を処理します。碑文谷氏は「遺体との別れは遺族にとって精神的に極めて過酷なものである。また遺体の処理が済まない間は、遺族にとって遺体は、亡骸であり死んだ存在であると頭でいくら理解していても、依然として愛する家族そのものであるという感情からは離れられない」と述べています。日本で一般的な火葬では、骨上げの儀式があり、死が現実であることを、非常にはっきりした形で確認する事になります。
葬儀の後の儀礼
日本での葬儀のうち95%は仏式で行われています。仏式で葬儀を行った場合、中陰の間、故人が死亡してから数えて7日ごとに、初七日、二七日、三七日・・・七七日(四十九日)までの忌日があり、最近は簡略化の傾向がありますが、知人、遺族、親族、などが集まって焼香をあげたり、僧侶にお経を読んでもらったりする供養を行います。定期的に遺族を訪れ、故人について語る、というグリーフケア的にも非常に意味のある伝統と言ってよいと思います。また、死亡から百日目には百か日法要が行われます。この法要の事を「出苦忌(しゅっくき)」または「卒哭忌(そつこくき)」とも言い、見ての通り、、悲しみ泣き明かした日々に一度気持ちの整理をし悲しみから卒業するための儀礼ででもあります。
仏教ではその後も一周忌、三周忌と法要があり、遺された者へのサポートが伝統的に行われてきました。
それ以外にも、伝統的な方法がグリーフへの適応に寄与している例に仏壇が挙げられます。日本では家庭に仏壇がある事も多いですが、仏壇は座り、向き合い、故人と対話するという形を自然に提供し、グリーフワークを進めていきます。
墓
墓には、「ご遺骨の収蔵場所」という機能のほかに、いくつかの役割や意味があると考えられます。たとえば、
- 家や家の継続性のシンボル・家としての弔いのシンボル
- 先祖を祀り、感謝する場
- 故人との繋がりの場・繋がりの媒介ツール
「家」という意識にどう反応するかは人それぞれだと思いますが、墓は「自分が一人でここに存在するのではない」、つまり、自分は親や子といった継続性の中で存在するという事のシンボルではないかと考えられます。現代でも「月に一度は、月命日に必ず墓参りに行く」という人は少なくなく、お墓が故人との対話の場、繋がりのツールとなっている事は確かです。
しかし同時に、墓は「家」のシンボルで、残された者にとっては押し付けられた儀礼や、気持ちにそぐわない事(暗くじめじめした所に故人を閉じ込める)でもあるという人もいます。
現代の葬儀や儀礼の変化と問題点
「なぜグリーフケアが必要か」、の変わる死を取り巻く環境で詳しく見たように、現代の死や葬儀を取り巻く環境は大きく変化して来ています。地域社会で行っていた葬儀は葬儀社から購入するサービスに代わり、文字通り「儀礼的」になってきています。葬儀に対する考え方の変化、合理主義、葬儀社の「暴利をむさぼる葬儀社」というイメージから、葬儀は出来るだけ簡単に、お金をかけず行うのがよい、といった意識が蔓延しています。葬儀に呼ぶことを、人に迷惑をかけると考え、葬儀に呼ばれる事を迷惑と感じる人が増えています。都市部では葬儀を一切行わない「直葬」が急増し、先に見た葬儀の意味のうち、「遺体処理」の部分だけの葬儀まで現れてきました。
葬儀後の儀礼についても、葬儀の時に初七日を一緒にやるのは当たり前になり、中には「何度も足を運んでもらうのは悪いから」と言う理由で四十九日まで一緒に執り行ってしまケースも増え、ますます故人を中心に人が集まり、遺された者を支える仕組みが弱くなっているのが現状です。葬儀や儀礼が、必ずしも宗教的である必要、華美や盛大である必要はありませんが、葬儀の意味を、今一度考えてみる必要があるのではないでしょうか。
墓に関しても、今日の少子化社会では、従来型の「墓を長男が継いでいく」という承継を前提とした墓の維持は困難になっています。その中から、承継を前提としない墓が出てきたり、散骨や樹木葬などの新しい方法も認知度が高まっています。従来型ではない墓(遺骨の行方と言った方が適切か)には、遺された者の故人への思いを表現する事、故人の人となりを伝えて行くことがよりできるようになってると思います。この辺り、代替的墓については、上記同様【お墓はなくてもだいじょうぶ】をご覧ください。
新しい儀式の創造
キャサリン・M・サンダースは「死別の悲しみを癒すアドバイスブック」の中でこういった面白い考えを提案しています。サンダースによると、通常儀式というのはその目的が何であれ、「断絶」「移行」「(再)結合」という3つの段階からなり経つか、3つの段階の一部分を担っているというのです。たとえは、葬儀は「断絶」であり、成人式は思春期から大人への「移行」、結婚は「(再)結合」であると言います。そして、サンダースは、葬儀が「断絶」のみを意味していることに着目し、ある人物の死について、「移行」と「(再)結合」の儀式が欠けているように思われるので、新しい「追悼のための儀式」を行うことも良いのではないかと述べています。
このように、儀式は必ずしも公的なものではなくても、私的な、自分だけのための物であっても良いのです。具体的なアイディアについては「実践的なグリーフとの付き合い方」セクションの「儀礼を上手に利用する」をご覧ください。