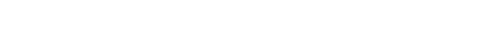喪失への適応を肉体への傷に例える
喪失と喪失への適応を肉体の傷に例える事
C.M.パークスはその著書、「死別 ― 遺された人たちを支えるために ― 」の中で、子細に「肢の喪失」と、「死別による配偶者の喪失」を比較し、「健常者から肢切断者になる心理社会的推移は、多くの点で配偶者を亡くす心理的社会的移行期と同質の苦痛を伴う時間のかかるプロセスである」、また、グリーフは「傷と同じように徐々に治癒するのが普通だが、(化膿して)治らなかったり、また傷口が開いてしまったりする」と結論付けている。
ここでは比較自体を紹介するのが目的ではなく、肉低的な傷と喪失のアナロジー(類似点)を探ることで、グリーフの痛みと回復への理解の一助となる事を狙いたいと思います。
トラウマ的体験
四肢の切断が、病気などのために計画的の行われたのか、事故などで突如失われたのかに関わらず、肢を失ったものは大きなトラウマの影響をうけます。配偶者の死の直後と同じように、不安、緊張、落ち着きのなさ、不眠が見られ、そして、怒りや不公平感も訪れます。パークスは言います。「それはちょうど未亡人が夫婦者を見たらいつも,、『どうしてこんなことが私に起こったのかと思わずにられ ない』と言うように、肢切断者の多くは健康で障害を持っていない人を見ると羨望を感じると認めている」と。肢を失ったものはその怒りを周りの人間に向けたり、自分を責めることも多いと言います。
失われた物
パークスによると、「配偶者を亡くした妻が夫の姿を探すように」失われた肢を求めて、患者が病院中を徘徊することはないが、6割以上の患者が、どのように切断された肢が処理されたのかに少なからず心配をしていたという。中には、「もしかしたら自分の脚は研究のために保存されているかもしれない」と妄想する者もいたという。また、未亡人が夫の実在を感じるように、医学的には「幻影肢」と呼ばれる「実際にはない足の実在感を感じる」人もいる。
しかしここで重要なのは、肢を失った者が喪失と考えているのは足や、手、そのものではなく、それらを使って行っていたこと、つまり、手足の機能であり、それを使ってしていた事をどんなに恋しく思うかを語ったという。伴侶を亡くした人は夫・妻を亡くしたには違いはないのだが、夫・妻という役割も一緒に失うことになるのと同じと考えても良いだろう。
元には戻れない悲しみ
パークスは、肢を失った者の6割以上は、肢を失った事実を忘れようと努力しているが、常に思い起こさせられ、その葛藤のつど、もう帰ってこない、不自由のない世界を切望する苦しみが戻ってくる、といいます。この「元には戻れない」という感情は多くの患者が繰り返し訴えるテーマです。「自分の身体の一部が除去されてしまったと感じて、もはや元通りの世界に戻れないのです」。他のひとりは「自分は不具者になったと感じると、もう二度と同じ自分に戻れないことが判るのです。心の底ではひどく傷ついているのです」と言う。
新しい意味の追求
しかし私は、パークスの外傷とグリーフのアナロジーは不完全だと考えます。パークスの描く、四肢の損失とグリーフのアナロジーは、「肢を失った人は悲しむけれども、傷は癒え、機能は回復するのだ」と言う側面だけしかとらえていません。もっと詳しく言えば、医者に「脚を切断して、それからどうなるのか」と尋ねてみた時と同じような感じです。医者は 「切断直後はショックもあるだろうし、痛みもあるだろう。大切な機能が失われて、悲しく感じられるだろう。しかし、現代の医療では、切断直後から正常な日常生活への回復を期待して、義足装着訓練をスムーズに行うために、傷の手当ても良くしている。傷は、時間がかかるかもしれないが徐々に癒えていく。義足もいい物が出来てきた。リハビリも、効率的なプログラムが用意されています。そう遠くないうちに、ずいぶん健常者と同じような生活が出来る。ダンスだってできるようになる。」と言うのです。良くなる、と言うのです。ある意味、極めて、段階論やフェーズ論に近い、全体像しか描いていない事に気が付きます。
しかし、奇しくもパークスはこういった観察も披露しています。
私が面接した四十六名の肢切断者のうち、肢切断から1年後でもまだうつ状態で社会から引きこもっていた者が十二名いた。そのほとんどの者が主治医が(その肢切断者の身体能力からして)予期していたように自ら進んで義足を使おうとは全くしなかったので「やろうとする気がない」と非難されがちだった。事実、数名の男女は、自分たちは一生障害者なのだと思い込んでいるようであり、またそのように思い込んでいるために、おそらく一生障害者となるかもしれない。
切断した傷は、緩やかに回復するかもしれない。歩行などの機能は回復するかもしれない。しかし、自らの人生を、肢はなくても「全き」人間として生きていくには、それだけでは不十分なのだという事です。
肢を失った人は、死による喪失と同じように、今まで信じてきた価値や想定の世界を失い、戸惑います。肢だけではなく、今まで考えてきた未来への希望も失われます。自己の持つ人生のイメージと突きつけられた現実のはざまで、怒り、不公平感は増し、だれかれに突っかかっていくかもしれません。病院やリハビリの担当医は、リハビリの開始を早く始めるようにせかしますが、リハビリを始めるには意志が必要なことがわかっていないかのようです。切断直後は興奮していたのか、意地のようにリハビリを始めても、傷の痛みが落ち着くころにはリハビリの意味が感じられず、もう、何もする気が起きないかもしれません。そこから、肢を失っても自分の人生を、自分として有意義に、「障害者としてではなく」生きるところにたどり着くまでにはグリーフワークが、新しい認知の枠組みが必要なのです。
元Jリーグのサッカー選手であった、車いすバスケットボール男子日本代表の京谷和幸選手は、初めて車いすバスケットに出会ったころについてこう振り返っています。「しょせん障害者のスポーツだって思ってしまった自分もいたりして。逃げたかったんですね。プロサッカー選手だった自分が車いすバスケをやって、恥をかいたらどうしよ うと周りの目が気になっていたんですね。そんな醜態をさらすくらいなら、プロサッカー選手だったころのままの自分でいたかった」 (NHK厚生文化事業団のインタビューより)。
いま、京谷和幸選手はこういいます。「(人間的に成長したと感じているので)今では事故に遭ったことすら感謝しているんです。当時はサッカーができなくなって、「なんでオレからサッカーを奪ってしまうんだ」って思いましたけど、今ではそれも良かったのかなって」。ここにはパラダイムシフトが起こっています。